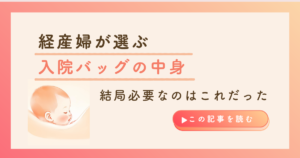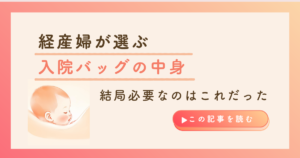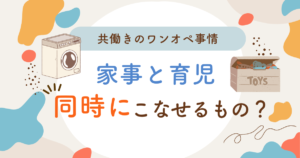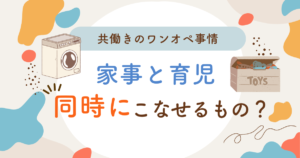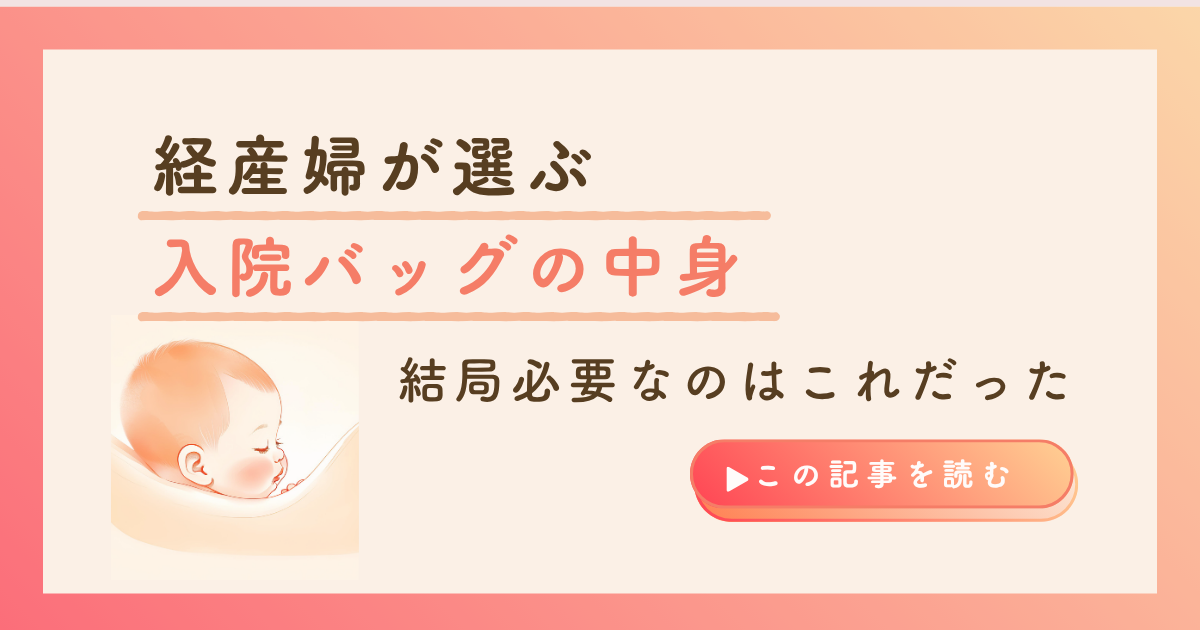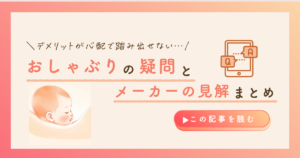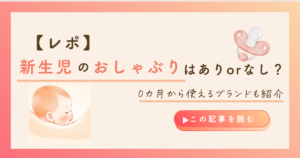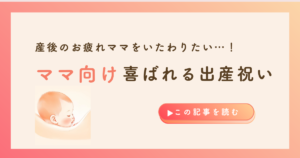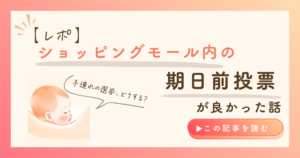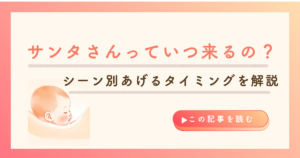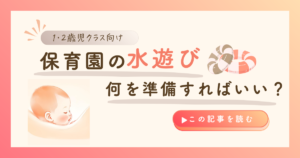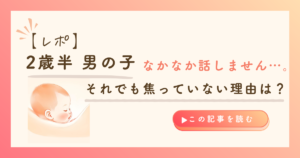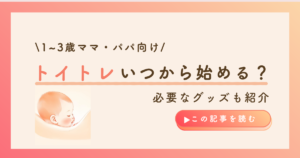出産時に持って行くカバンには、出産前から出産中に使用するものを入れる「陣痛バッグ」と出産後の入院中に使用するものを入れる「入院バッグ」があります。
それぞれ何を入れると良いか、2回の出産経験をもとに紹介します。
経産婦が選ぶ出産時のバッグの中身
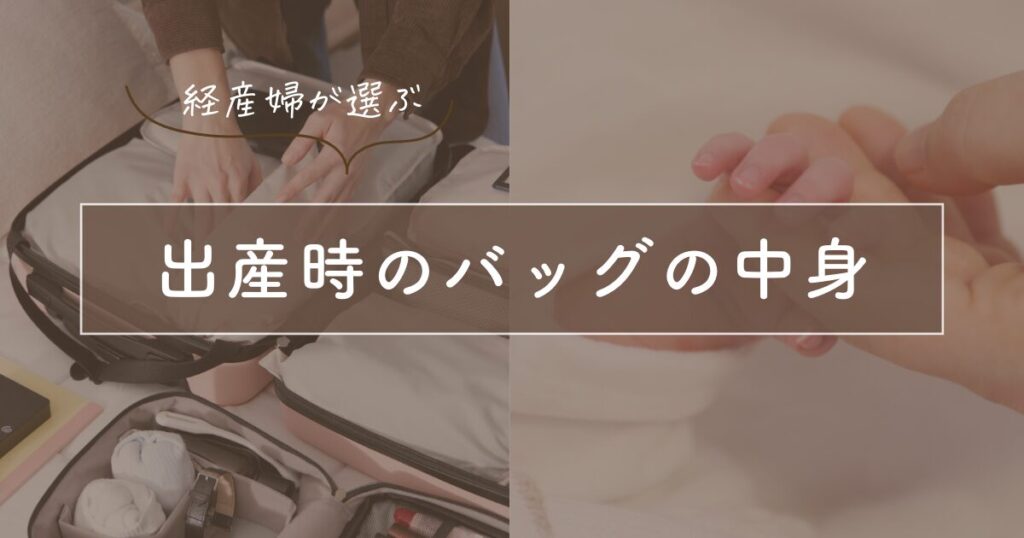
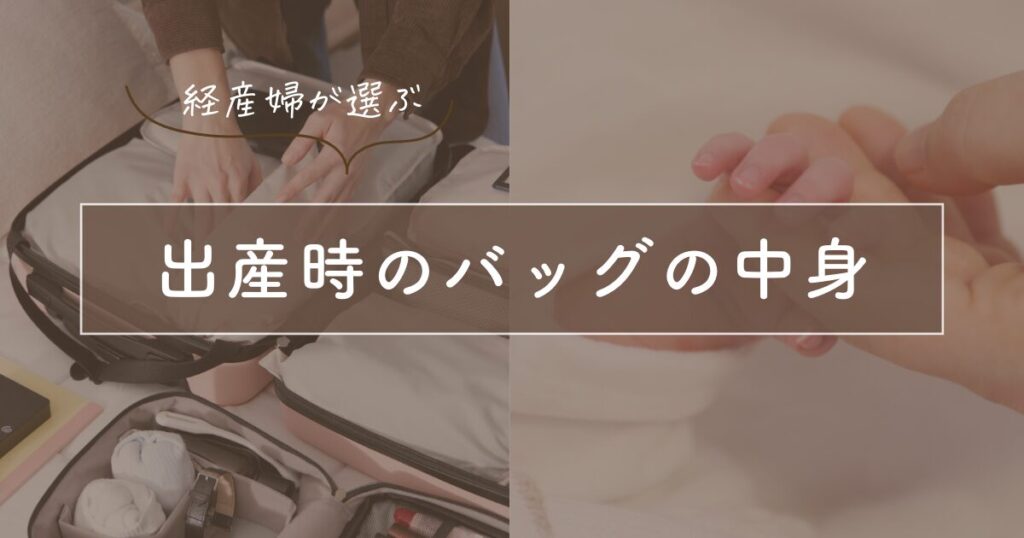
いきなりですが、私は2025年7月末に、無痛分娩(陣痛が来てからのオンデマンド無痛分娩)で2回目の出産をしました。出産の際に用意したバッグの中身を、まず紹介します。
陣痛バッグ
1.産院の書類
2.母子手帳
3.横になった状態でも飲めるストロー→おすすめの商品はこちら
4.ミラーレスカメラ
5.産褥ショーツ(1枚)
6.普段から使っている財布
7.(財布とは別に)小銭入れ
8.車の鍵
9.家の鍵
10.スマホ
11.メガネ
12.500mlのペットボトル(2本)
13.ゼリー飲料
14.鉄剤・ビタミン剤(後項に詳細)
15.モバイルバッテリー→おすすめの商品はこちら
16.印鑑



陣痛バッグは最低限必要な書類と陣痛中の軽食のみを用意して、貴重品は当日入れました!
現金はどのくらい持って行く?
出産前後から退院までに現金が必要になる機会はそれほど多くありません。
・自動販売機で飲み物を買うとき
・コインランドリーを使用するとき
・公衆電話を使用するとき
高額な支払いは必要ないため、小銭を中心に持っておくと良いでしょう。
退院時の支払いに関しては、現金での支払いのみとなっている産院もあります。都内の場合、国の助成を差し引いても10万円単位での手出しが必要になることもあるかもしれません。
ただ、家族が退院時に付き添ってくれる場合は、妊婦さん自身がお金を持っておく必要はありません。



2度目の出産時、部屋の鍵をかけないように言われました。
部屋にシャワーが付いていましたが、シャワーの際も施錠はNGでしたよ。
入院中も沐浴指導や粉ミルクの調乳説明など、部屋を離れる機会もゼロではありません。現金は小銭を中心に必要最低限にしましょう。



入院時にあらかじめ支給されたオムツを使い切ってしまう可能性もあります。
追加で購入することもできますが、退院時の支払いに合算される形が一般的です。
軽食について
陣痛のきたタイミングによっては、ご飯を食べ損ねることもあります。



2度目の出産時は夕方に陣痛が来たため、産院の夕食に間に合いませんでした。
結果として家族へ差し入れてもらう形をとりましたが、陣痛から出産まで何時間かかるか分からないため、家族はご飯だけを差し入れて帰ってもらわなければならないこともあります。
出産は体力勝負なところもあり、空腹は身にこたえます。あらかじめ用意していきたいものの、陣痛が来てからコンビニへ寄るのは現実的ではありません。
破水をしていたら即向かった方が良く、破水をしていなくてもいつ破水が起きてもおかしくないためです。
そのため、ゼリー飲料やエネルギーバーなどを鞄へ入れておき、もし家に菓子パンなどがあれば追加で入れて持って行くのが良いのではないでしょうか。
横になっても飲めるストロー
2度目の出産では、以下の商品を持って行きました。
1度目の出産では、100均のものを持って行きましたが、普通のまっすぐのストローとペットボトルキャップがくっついたもので、傾けたり残量が少なくなると上手く飲めずにいまいちでした。



スケーターのペットボトルストローは、やわらかいシリコンのストローで柔軟に曲がります。
長さも長めで、2リットルの大きなペットボトルでも問題なく使用できるくらいです。
陣痛中はもちろん、産後は排尿・排便が鈍ることがあったり※、高頻度で授乳をしたりする人もいるため積極的に水分補給を行いたいところです。
※出典:アンケート調査にみる産後排尿障害のリスク因子 | 一般社団法人関東連合産科婦人科学会
鉄剤・ビタミン剤
サプリについては、私は出産前の妊婦健診時に血圧の数値が低くクリニックから処方されており、出産まで毎日服用していました。
そのため、陣痛バッグにも入れて持っていったのですが、サプリの服用については自己判断はせずかかりつけ医に確認しましょう。



無痛分娩を行う方は、特定のサプリの服用がNGになっている場合※もあります。
※出典:無痛分娩を – 千船病院
入院バッグ
ママ用
1.前あきパジャマ(3セット)
2.産褥ショーツ(3セット)
3.授乳ブラ(3セット)→おすすめの商品はこちら
4.顔パック→おすすめの商品はこちら
5.産褥パッド→おすすめの商品はこちら
6.ヘアドライタオル→おすすめの商品はこちら
8.骨盤ベルト→おすすめの商品はこちら
9.長めの充電ケーブル
10.パソコン
11.正中線ケアクリーム→おすすめの商品はこちら
12.マスク
13.ウェットティッシュ
14.着圧ソックス
15.ビニールバッグ(3セット)



私の入院先は「手ぶら入院OK」くらい病院側のアメニティが豊富だったので、「自分のものを使いたい」と思ったものだけを用意しました。
上記のリストの中でいうと、授乳ブラ・骨盤ベルト・着圧ソックスは、特に用意して良かったです。
授乳ブラ
授乳ブラとは両肩の紐の部分の前側にホックが付いており、外すと片胸だけ出せるようになっています。


1人目のときはユニ●ロのブラトップにしていましたが、とにかく新生児は頻回授乳のため、地味に肩紐を抜くのが大変でした。
片胸だけ出すことが難しく両肩を外すことになってしまい、結果さらしのような状態に。授乳ブラなら、肩紐は外さずに片胸を出せます。
この良い点は、射乳(しゃにゅう)対策になることです。片胸を吸われているとき、吸われていない方の胸から出てしまい服を濡らしてしまうことがあるかもしれません。
授乳ブラならブラカップは外さないためマミーパッドで受け止められます。
骨盤ベルト
骨盤ベルトは妊娠中から付けている人も多いでしょう。出産時に赤ちゃんが通るために、骨盤は妊娠時からゆっくり広がっていきます。
出産を終えると骨盤も戻っていきますが、「なるべく早くから正しい位置でしっかり固定できるものを付けること」が大切です。
以下、少し長いですが引用になります。→プルダウンで開閉できます
・出産時の骨盤ってどうなるのか
左右対称に配置されている寛骨と中央の仙骨が骨盤です。
これらの骨を繋いでいるのが関節であり、靭帯であり、筋肉です。
出産時にはこの骨盤の中を赤ちゃんはゆっくり下りてきます。
赤ちゃんを下りやすくするため、妊娠中から骨盤は
だんだんと広がっていくのですが、
広げるためには靭帯や筋肉を緩めなくてはなりません。
さらに出産時には大幅に広げなくてはいけないので、
ほぼ骨盤全体は原型を留めないと思ってください。
・ゆっくり戻る骨盤
腰回り(骨盤)が緩むと、人間は立ったり歩いたり、
下腹部に力が入らない状態で無理に動くことは
おすすめできません。
骨盤周りの靭帯や筋肉は、「戻ります」。
しかし、伸びて緩んでしまったものはゴムとは違い、
ゆっくり2ヶ月ほどかけて戻ることになります。
焦って元通りにすることはできませんし、
戻る過程で家事や育児など過度な負荷が骨盤にかかり、
戻ることが容易でなくなると、
ずっと不調が続く可能性がでてきます。
出典:産後骨盤ベルトしないとどうなる|加西市の整体は国家資格者20年の実績|豊田接骨院。腰痛・骨盤矯正・自律神経症状の改善なら豊田接骨院



産院によっては、産後すぐ骨盤矯正のマッサージが付いてくるところもありますよね。
私も施術を受けたのですが、担当の方にはガードルのような広めのベルトタイプをおすすめされました。(※)
※個人の経験談のため、有識者にご確認ください
私自身は、妊娠中から産後まで一貫して使える「トコちゃんベルト」を4年前の長男出産時から使用しています。
ただ、産後に特化した商品もあるので検討してみてくださいね。前述したガードルタイプは以下のような感じです。
赤ちゃん用
1.爪切り→おすすめの商品はこちら
2.リップクリーム→おすすめの商品はこちら
3.手形スタンプ台→おすすめの商品はこちら
新生児用 爪切り



爪に関しては、産院によって病院側で切ってくれるところとママが自分で切るところがあるようです。
赤ちゃんによって違うのですが、長男は顔に手をよく持って行く子だったため引っかき傷がたくさんできました。
新生児は目がほとんど見えていない上に力加減も調整できないので、食い込むように爪を立ててしまうことがありましたよ。
新生児から使える子ども用の爪切り(ハサミ)があるので、持って行っても良いでしょう。私はピジョンとコンビを使ったことがあります。



大きな違いは、ピジョンの方が刃が短めです。個人的にはコンビの方が切りやすかったです。
ただ、新生児の爪はとにかく小さいため、深爪したり切ったことによって逆にとがってしまうことも。爪やすりならハサミよりはリスクを減らせます。



コンビの爪やすりは、ヘッドを付け替えて使用できるのでおすすめです。
おまけ:後から「持って行ってもよかった」と思ったもの
陣痛バッグ
1.レジャーシートorゴミ袋
2.うちわ
入院バッグ
1.「JUST BORN」プレート(カード)
2.ふわふわ系のブランケット



レジャーシート(orゴミ袋)は、病院へ向かっている際に破水する可能性があったため、入れておけばよかったと思いました。
おまけのおまけ:自分は不要だったが人によっては必要だと思うもの
陣痛バッグ
1.汗拭きシート
2.ハンディファン
3.テニスボール(いきみ逃し用)
入院バッグ
1.小分けのお菓子
2.アイマスク
3.充電式カイロ
4.適度な硬さの円座クッション→おすすめの商品はこちら



出産時期は人それぞれのため、寒さor暑さへの対策は考えていきたいですね。
小分けのお菓子
産院の夕食は、おそらくは片付けの関係でやや早めです。



1度目の出産時の産院は19時ごろ、2度目の出産時の産院は18時ごろが配膳の時間でした。
翌日の朝食は、産院によって異なるもののおおよそ8時ごろです。夕食から朝食までの間が長めなことは留意しておきましょう。
「夜は食べずに我慢して寝てしまえば良い」と思うかもしれませんが、出産後は夜間の新生児のお世話があるかもしれません。
クリニックによっては、出産当日から夜間も母子同室を推奨されるところもあります。(私は1度目の出産時の産院は、同室が基本の方針でした。)
母乳による授乳の場合、3時間おきにあげていると空腹を感じる可能性もあります。ストレスを感じないように少量の食べ物を持っておくと安心です。
(余談)母乳育児をメインに考えている人へ



産後すぐは、乳腺が開通していない人もいるでしょう。
詰まりによる乳腺炎が心配なため、お菓子の種類は、少し気を付けておくと良いかもしれませんね。
チョコレートなどの脂肪分の多いものは、疲れや授乳間隔など複数の要因が合わさると母乳の出に影響を及ぼす可能性も否定できません。※
※出典:授乳中にチョコを食べても大丈夫?母乳への影響は?|えつき助産院



私も混合授乳中ですが、おすすめは甘い飲料です。甘みを我慢せず、水分補給になります。
あとはドライフルーツなども、持ち運びやすく少量で満足できます。
適度な硬さの円座クッション
出産時に「会陰切開(えいんせっかい)」をする人も多いでしょう。産後数日は、座るときに痛みを感じます。その際に活躍するのが円座クッションです。
円座クッションは病院側で用意されていることも多いのですが、質感が硬すぎるものもあります。



硬い=沈みにくさがメリットなのですが、産後用ではなく、坐骨神経痛などの人に向けた商品の可能性もあります。
一方で、柔らかすぎると沈み込みによって炎症部分を圧迫してしまい、痛みが増してしまうかもしれません。
もし、使用した際に違和感を感じるようであれば、自分で購入して途中から持ち込んでも良いでしょう。
発送が早いネットショップを選べば、翌日か翌々日配送されるため入院中に間に合うかもしれません。
妊娠中、いつからバッグを用意した
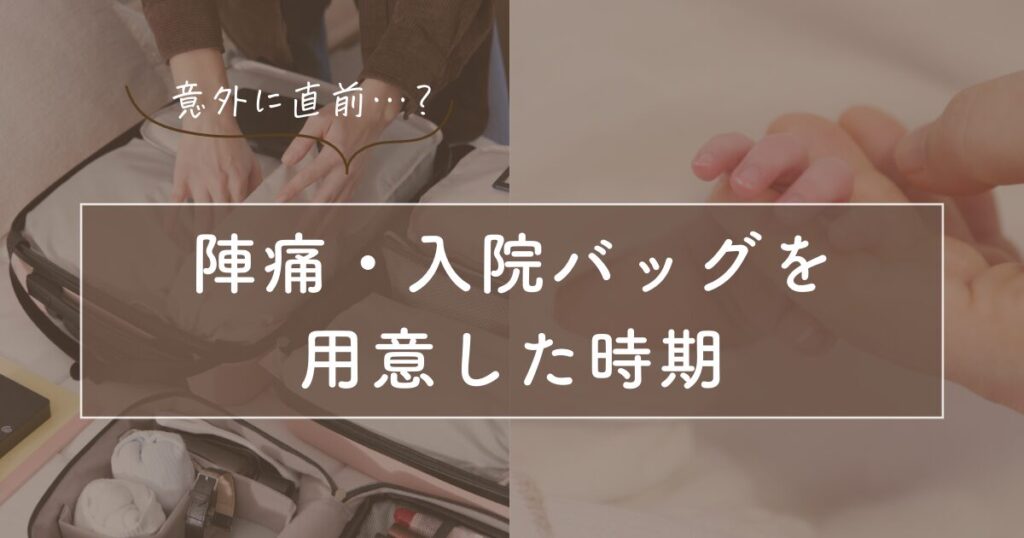
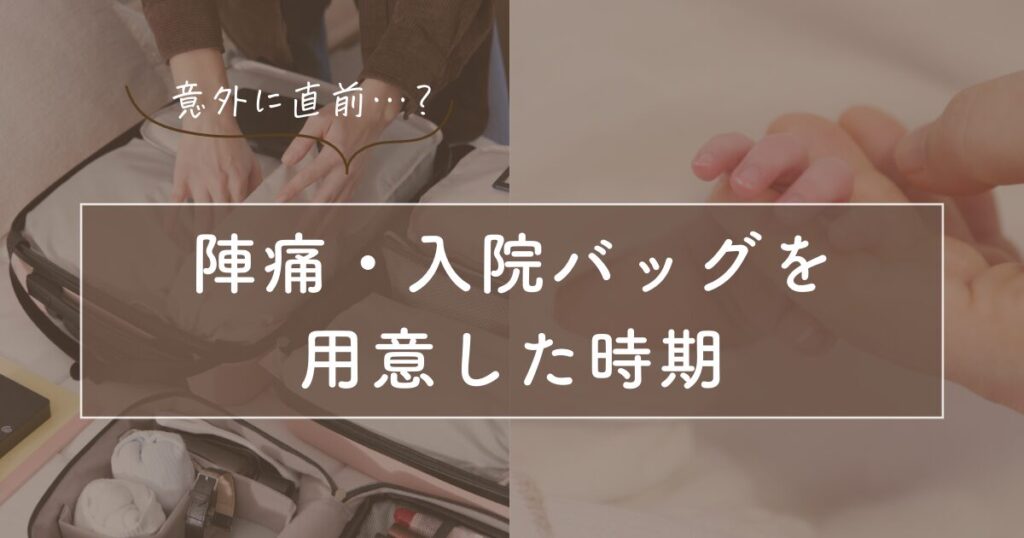
陣痛バッグ・入院バッグはいつから用意するのが良いのでしょうか。私は今回、2度目の出産だったことと、上の子のお世話に忙殺される中でつい、後回しにしてしまいました。
ただ、妊娠後期の体調の悪さも考えると、中期に準備するとより良かったなと思います!
2回目の出産前は、だいぶゆっくりめ。臨月から
らの用意
2回目の妊娠中は上の子のお世話をしながらだったため、臨月(36週ごろ)に入ってから何日かに分けて少しずつ中身を入れ替えながら持って行く量を決めました。



ただ、これは正期産(37週~)に入ってから生まれるだろうという妊婦健診の経過があってからこそです。
少し早めに産まれてくる可能性も当然ありますよね。
また、臨月はお腹の大きさも妊娠中で最大になります。
不思議なことに、赤ちゃんの体重増加が1週間で数百グラムだとしても、体感としてお腹は弾けそうなくらい張っていますし、体を動かすのにもひと苦労です。人によっては、後期づわりになっていることもあります。
育児情報の本などでは「7~8カ月ごろから用意しましょう」と書いてありますが、中期の段階で用意できるのであれば早めの準備がおすすめです。
(余談)遅くなった一因は手持ちのマタニティ用品の数
私の場合ですが、妊娠期間中、マタニティ関係のパジャマや下着はそこまで多めには用意していませんでした。初産のときのものをなるべく使って、買い足しは最小限にしたからったためです。
そのため、服は入院までの間、毎日「使用⇔洗濯」のサイクルで出払っている状態でした。私自身「陣痛が来てから入れればいいや」と鷹揚に構えていたところもあります。
では、陣痛のときに準備する余裕はあったのか



(これは人によると思います)私は経産婦ですが、今回の入院時もバタバタしてしまい、持って行き忘れがありました。
私の場合、入院当日は、日中鈍痛に耐え、陣痛のような腰痛が我慢できなくなった夕方の段階で産院に連絡し「とりあえず今から来てください」と言われました。
このときに「何分で来られますか?」と聞かれて、バッファをとらずに最短の時間を伝えてしまったため焦りが生まれました。
また、経験上そのまま入院になると最悪そのまま出産になりお風呂に入れないことが分かっていたので、慌ててシャワーだけ浴びました。※
痛みの中で身支度を優先したため、結果的に準備されたバッグを持って行くのが精一杯でした。
※破水した場合、シャワーNGとしている産院もあるため各々確認してください。
陣痛バッグと入院バッグは分けた?
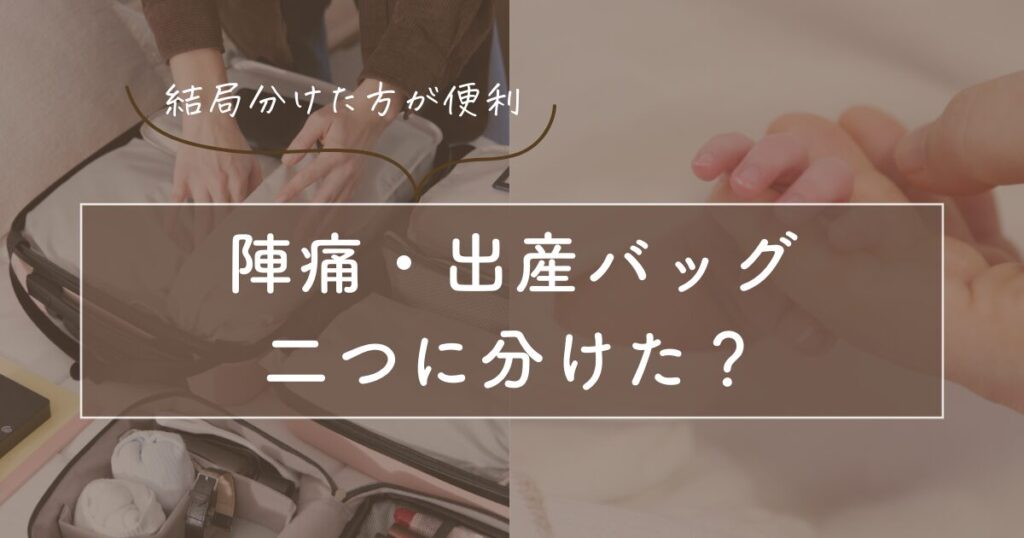
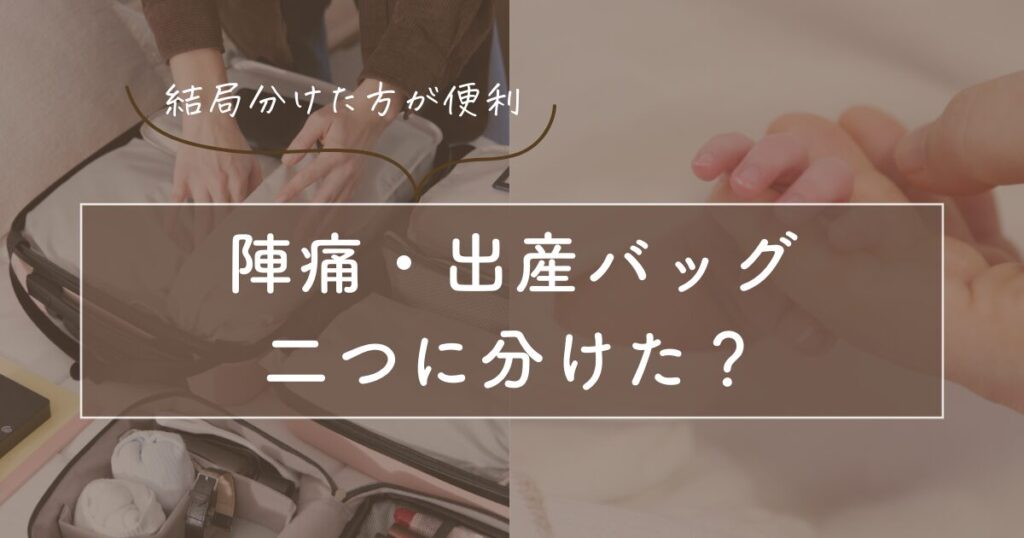
ここまでに何度か言及してきた「陣痛バッグ」と「入院バッグ」。違いを知っていますか?
・陣痛バッグ:陣痛による入院から出産までに必要なものを集めたバッグ
・入院バッグ:出産後の入院から退院までに必要なものを集めたバッグ
二つに分けた方が良いのかどうか考えていきましょう。
荷物量でバッグの数は変わるが、分けた方がいい
前述のように、産院側で入院バッグの中身をほとんど用意してくれる場合やなるべく荷物を少なくしたい人は、入院バッグと陣痛を一つにまとめても問題ありません。
ただ、バッグインバッグなどで「出産までに使うもの」と「出産後に使うもの」を分けておくと出し入れがスムーズですよ。



2度目の出産時に感じたのですが、陣痛時は分娩台から動けないため、自分でバッグの中身を出し入れするのは難しいです。
必要なものはパートナーや助産師さんに取ってもらう形になりますが、荷物が多い場合、自分でもどこへ入れたかうろ覚えになってしまう可能性もあります。
なお、陣痛時も出産後の入院時も両方使用するものの場合は、先に使うことになる陣痛バッグの方へ入れておけば安心です。
退院時の荷物量が増える可能性も念頭に置いて
出産後は、産院からベビー用品メーカーの資料や試供品を配布されることがあります。手提げ袋に入っており、結構かさばるものです。
また、粉ミルクや紙オムツも一つずつは産院が用意してくれることが多いでしょう。入院中も使用しますが、使い切るよりも前に退院になりそのまま持ち帰ることも少なくありません。
さらに、入院中の面会で親族から出産祝いとして何かもらうことがあるかもしれません。箱状のものなどは、一つや二つでも鞄へ入れられないこともあります。
ボストンバッグのようなメインのバッグは一つでも良いですが、小さくたためるエコバックなども持っておくと便利です。



陣痛バッグと入院バッグを持って行く人は、陣痛バッグの中で入院中に使わないものを持ち帰り、もらったものを入れるスペースを作るのも一案です。
入院バッグの中身、参考にすると良いのは?
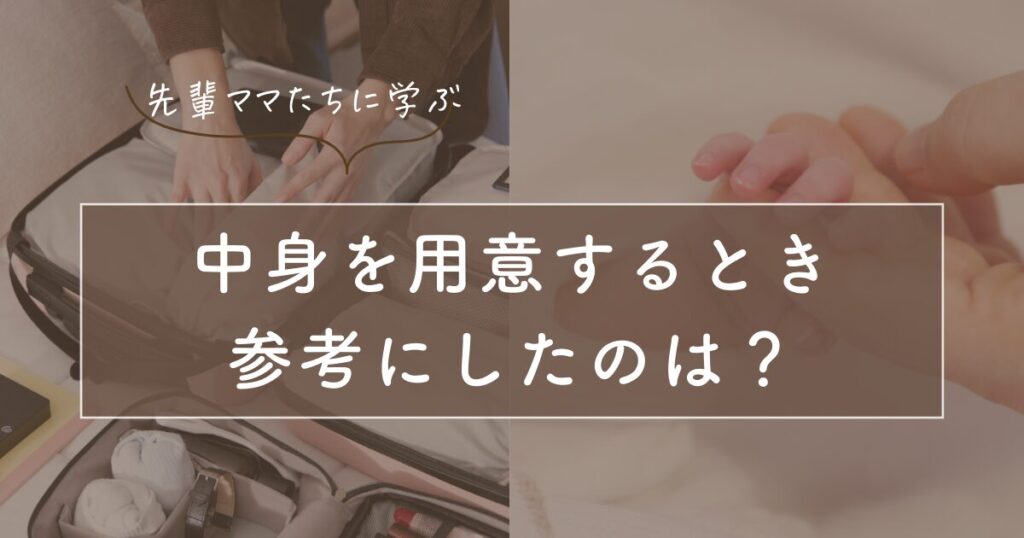
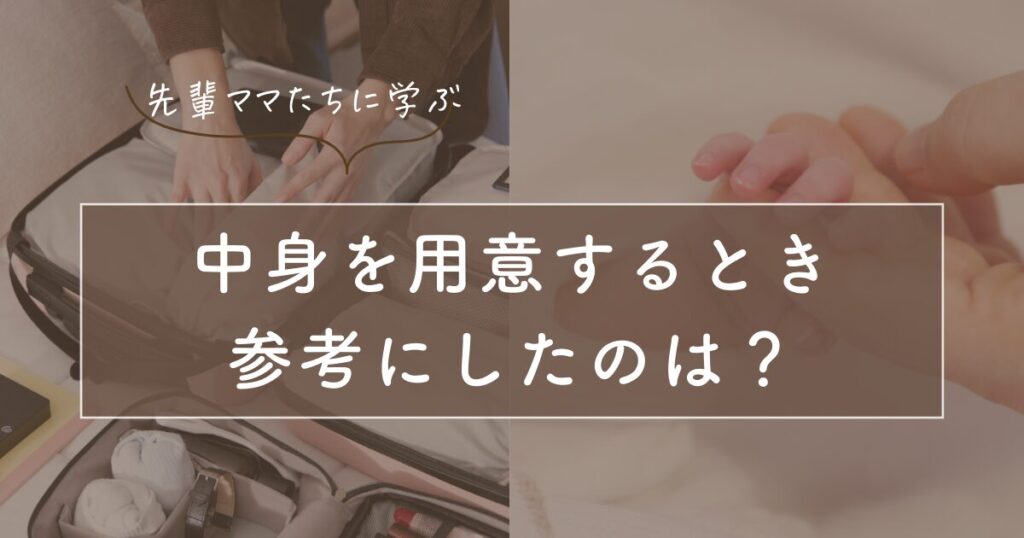
入院バッグは「あれもこれも必要な気がする」「あった方がいいはず」と量が多くなりがちです。ただ、陣痛や破水スタートで入院する場合、大荷物を運ぶ余裕がないこともあります。
余裕をもって準備を進めるために、参考にするものをまとめました。
入れるものを決めるときに参考にしたものは?
陣痛バッグや入院バッグを用意する際に参考にしたのは、以下のようなコンテンツです。
・赤ちゃん用品店:店内に置いてある無料のプレママ向け冊子
・YouTube:入院バッグの中身を紹介している動画
・Instagram:フィード・リールなどの投稿
なお、初産のときは、書店でプレママ向けの有料雑誌なども購入して必要なものを想像していました。
「産院のリスト+α」を用意する
SNSや書籍類で陣痛バッグや入院バッグに入れるものを調べると、「こんなに必要なの!?」と驚くかもしれません。
しかし、公開されているリストは、実際の必要度が低いものから高いものまで入っています。



主な理由として「個々人にとって必要なものの優先順位は異なる」ためです。
例えば、シャンプーやリンスについて「アメニティとして部屋にあるもので十分」と持ち物には含めない人もいるでしょう。一方で、普段と異なるものには抵抗があり、トラベルボトルに入れて家から持ち込みたい人もいます。
取捨選択は自分で行わなくてはなりませんが、初産婦さんは困ってしまうかもしれません。



出産が近づくと、産院から必要なもののリストが配布されるはずです。そこへ書かれているものは基本用意する形で良いでしょう。
産院によって「準備されているもの」や「必要になるもの」が異なります。
特に、歯ブラシやドライヤー、スリッパなど身支度に関するものが必要なリストに入っている場合、忘れると不便さを感じるはずです。
余談ですが、(私も含めて)企業の案内や個人の投稿には広告や個人の好みなどが少なからず反映されています。産院のリストを網羅した上で、参考にすると良いでしょう。
準備の流れ
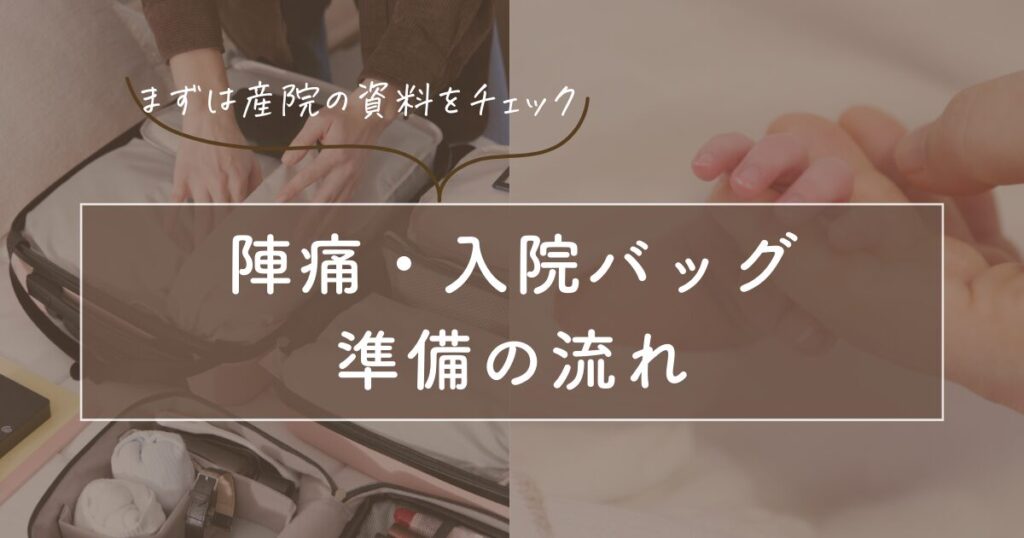
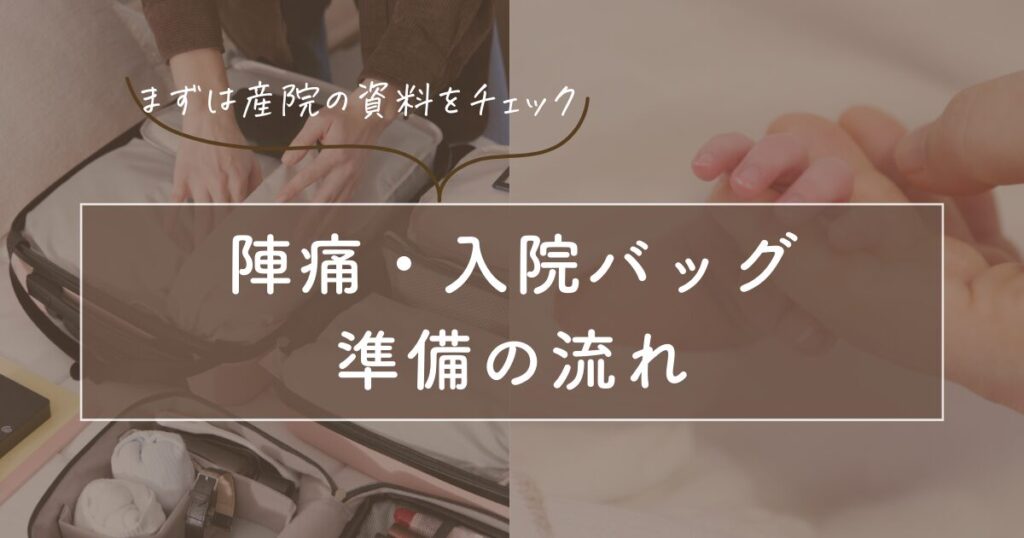
陣痛バッグや入院バッグをいざ準備するとなったときに、何か参考にするものがあると心強いですよね。
産院側から配布される必要なもののリストは押さえた上で、SNSの情報などから+αで持って行きたいものを考えましょう。
準備①:産院の「必要なものリスト」を確認
多くの産院では、入院中に必要なものについてホームページに記載されているか後期の妊婦健診時に資料が配られます。
私は2度別の産院を利用していますが、最初の産院は後期に母親学級という名の説明会がありそこで紙で必要なものが配布されました。
スリッパや歯ブラシなど、一通りのものはすべて持参が必要だったため、病院のリストのものはあらかじめそろえていきました。
2度目は反対に「入院時に最低限の荷物で済むこと」を重視しているクリニックで、ほぼ何も必要なものがありませんでした。
そのため、出産前の診察後、入院にあたっての留意事項を記載した資料の一つとしてアメニティのラインナップが書かれた紙を渡されました。



総合病院・産院・クリニックなど、出産場所によって全く異なるため、産む場所の資料はまず確認しましょう。
れるかどうかも事前に調べたうえで産院を決めると良いでしょう。
準備②「自分にとって欠かせないもの」を追加する
当たり前のことですが、陣痛バッグや入院バッグへ入れられるものには限界があります。自分にとって欠かせないもにプライオリティを高く置いてバッグの中身を作っていきましょう。
このときの「自分にとって欠かせないもの」は、さらに細分化できます。
・優先度 高:ないと生活に支障が出るもの
・優先度 中:なくても過ごせるけれど、ストレスを感じるもの



私の場合、優先度が高く、忘れずに持って行きたかったのは着圧ソックスでした。
1人目のとき、産後にむくみが出て辛いことを分かっていたからです。
後者は、例えば毎日欠かさず美顔・美肌ケアをしている人がいたとして、普段使っている全てのマッサージ器を持ち込むことは難しいでしょう。
ただ、本人にとってはないとストレスを感じるものになるでしょうから、100か0ではく、その中でも優先度が高に近いものを選べば良いのではないでしょうか。
入院後、追加したものはあった?
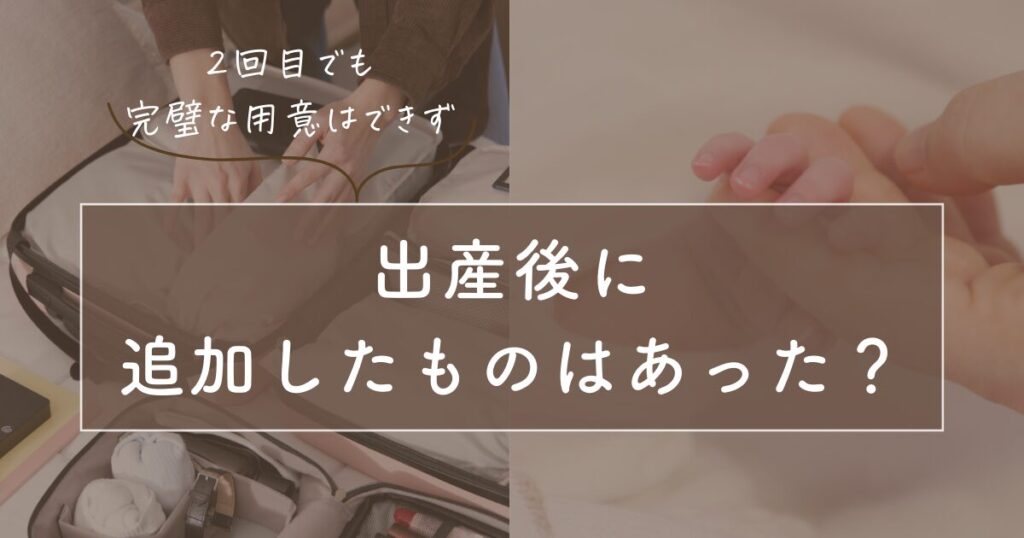
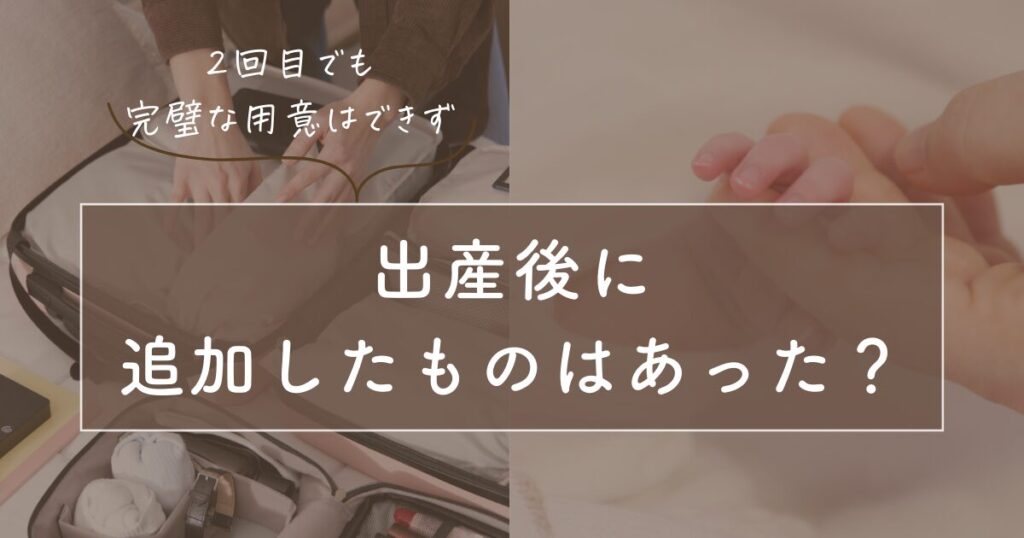
陣痛バッグ・入院バッグは「とにかくないと不安なものは入れておこう」と大荷物になりがちです。しかし、出産翌日以降に面会時間のある産院であれば、家族などに追加で持ってきてもらうことは可能ですよ。
母親と赤ちゃんそれぞれ、追加する可能性のあるものも紹介します。
「当日から次の面会時間まで」を乗り越えればOK
家族や両親、知人などが面会に来てくれるのであれば、そのときに持ってきてもらうこともできます。そのため、本当に自分で持って行かなければならないものは、実はそんなに多くないといえるでしょう。
そして、自分で持って行かなければならないもののうち、貴重品類に関してはあらかじめ入れておくのが難しい人も多いのではないでしょうか。



私も、家の鍵・財布・車の鍵・スマホ・普段使用しているクレカなども入った財布などは、陣痛が来ていざ病院へ行くとなったときに入れました。
対処法としては、バッグインバッグを作ることです。貴重品はミニバッグにまとめておくようにすると、普段の外出時にも楽ですし忘れ物が出る可能性も減ります。陣痛が来てからも慌てることなく数秒で準備ができるでしょう。
具体的に何を追加した?
後から追加するケースとしては、産む前は必要ないと思ってたけど意外に必要だったと感じるものが出てきたときです。
母親側としては、
・入院している部屋が寒かったor暑かった→衣類やブランケット類の追加
・授乳で乳頭が痛すぎる→保護クリームを買ってきてもらう
・乳腺炎になりかけているので冷やしたい→保冷剤を持ってきてもらう
などが考えられるでしょうか。
赤ちゃん側としては
・泣いてしまう→おしゃぶり
・吐き戻しが多い→ガーゼ、スタイ
・反射が何度も起こって寝てもすぐ起きてしまう→スワドル
などがあります。



赤ちゃんのお世話に関するものについては、入院中はプロの助産師さんへすぐ相談できる環境にいますよね。
自己判断で追加する前に聞いてみると良いでしょう。
出産用のバッグを作るときのポイント
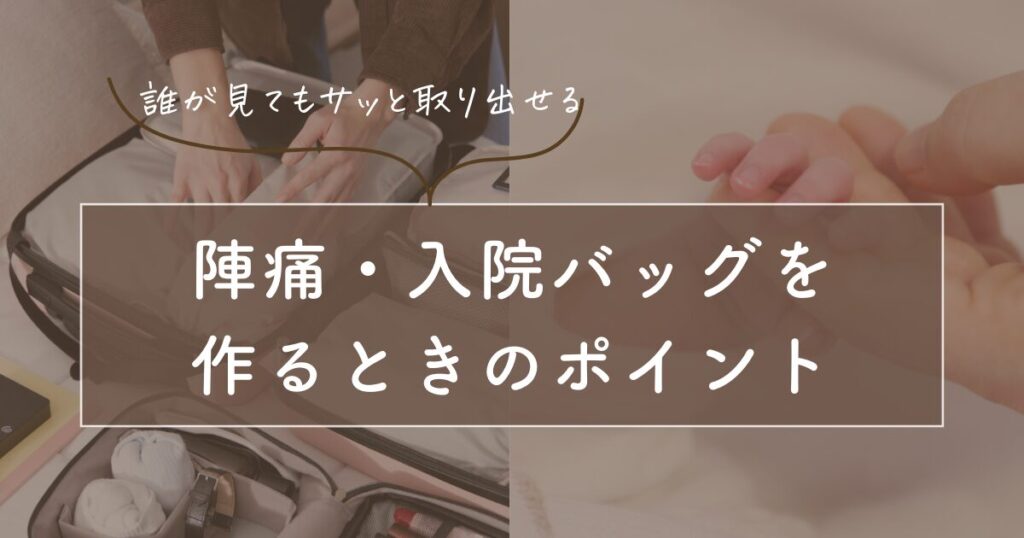
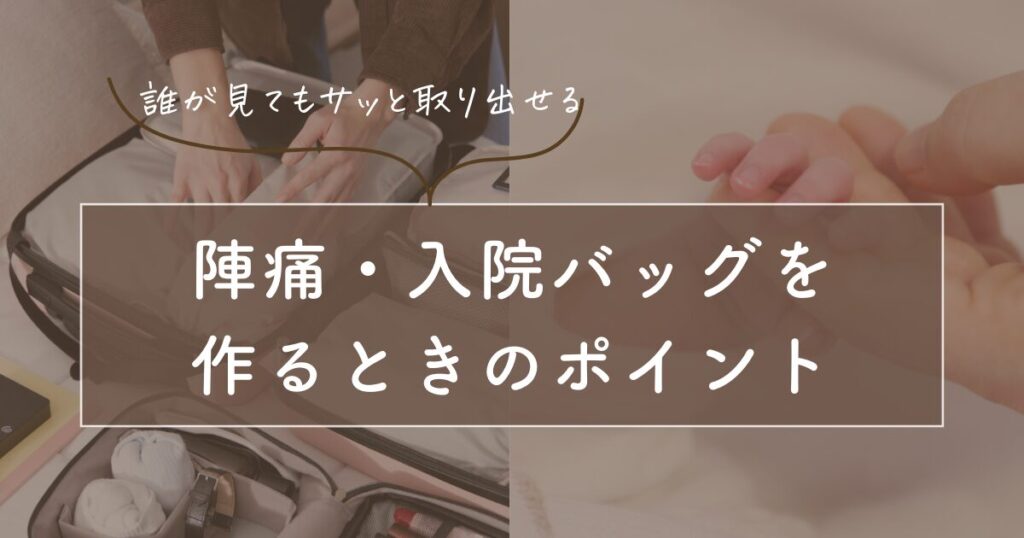
陣痛バッグと入院バッグは、それぞれ使うタイミングが異なります。特に、陣痛バッグは、自分以外の誰かが中身を触る可能性もゼロではありません。
準備する際のパッキングのポイントや入院中の中身の入れ替えについて紹介します。
「陣痛バッグ」の中身は誰が見ても取り出しやすいように
陣痛バッグは、出産中に使用する可能性があるものを入れるバッグです。そのため、家族や助産師さんなどが必要時に触る可能性があります。
来院後、即分娩台へ直行するときなどは、陣痛バッグの中を整理する余裕はありません。分娩台に固定された状態で、他の人に持って来たものを取ってもらうこともあります。



例えば、いきみ逃しのテニスボールやハンディファン、寝ながら飲めるストロー&飲料などです。
私は今回、ギリギリまで自宅で陣痛に耐えていたため、付いてすぐに分娩台へ直行でした。また、無痛分娩を希望しており、すぐに背中と腕に麻酔用のカテーテルを入れ、出産後まで動くことはありませんでした。
そのため、荷物はベッド脇に置いていたものの、自分で取りに行くことはできず取っててもらいましたよ。



他には、出産が進んできたころに、カメラやビデオ撮影の有無を聞かれました。
バースプランで「出産の様子を撮影してもらいたい」と書いている人は、カメラやビデオの用意はもちろん、助産師さんや病院側の担当者の方が取り出してすぐ撮影できるように、使用するレンズや設定を確認しておきましょう。
「入院バッグ」の中身は面会時に少しずつ持ち帰ってもらう
入院期間は経産婦なら3~4日、初産婦なら4~6日が一般的です。
入院中は以下のようなものをもらうことがあります。
・病院の入院中のスケジュールや退院後の検診の日程、費用の概算などの資料
・病院から命名紙や足形・手形のプレゼント
・子育て企業からのベビー用品の試供品、資料請求の案内
・粉ミルクやオムツの試供品
・面会に来てくれた人からの出産祝いや差し入れ



ありがたいことなのですが、企業からのベビー用品&ベビー教材の案内などは結構な量がありかさばります。
出産祝いも、病室へずっと置いておかなくても良いものもあるでしょう。
入院期間が数日あることもあり、「寝ているだけでは時間があまりそうだから持って行こう」とパソコンやタブレット端末、本やオーディオプレーヤーなどを入れている人もいるかもしれません。
また、かわいいわが子の姿を収めようとカメラやビデオカメラを持ち込んでいる人もいるでしょう。



ただ、思ったよりも産後のママは忙しく、すき間時間はあまりありません。※
念を入れてしっかり準備していくことは悪いことではありませんが、残り日数を見ながら、面会のタイミングで家族に少しずつ不要なものを持ち帰ってもらうのも一つです。
※(初産婦さん向け)入院中に入る主な予定



最後に、初産婦さん向けに入院中に入る予定を紹介します。意外に忙しくてびっくりしますよね。
入院中は赤ちゃんのお世話が第一優先として、空いている時間に助産師さんによる問診(体温・血圧検査)や沐浴指導、粉ミルクの調乳指導などが入ります。
また、母乳育児をする人は、胸が張って痛みが出たときに乳腺の開通マッサージや圧抜きをしてもらうこともあるでしょう。
産後、骨盤矯正のマッサージをしてくれるクリニックなら、母体の状況次第で「この後どうでしょう」と近々で施術が決まることも珍しくありません。
さらに、食事は朝・昼・おやつ・夜とほぼ3~4時間おきに配膳されます。食事の合間にシャワーも浴びますが、共用のシャワー室の場合は予約した時間の間に入らなければなりません。
退院前日には、母体の診察や新生児検診(2週間・1カ月)の予約、入院費用の概算の説明などもあるでしょう。



スケジュールを押さえた上で、必要なものを持って行きたいですね。
まとめ


陣痛バッグや入院バッグは、妊娠中で身体が重たい中で用意します。初産婦さんの場合は、出産後のベビー用品の購入などもあり、バタバタしていることでしょう。
「何を」「いつまでに」用意しなければならないのか、不安を感じている人もいるはずです。



最悪、赤ちゃんとママに関する書類・貴重品・下着&パジャマが1セットあれば、翌日以降家族に持ってきてもらうこともできます。
妊娠後期は、後期づわりや寝不足、尿漏れなど辛さを感じる時期です。無理のない範囲で用意してくださいね。